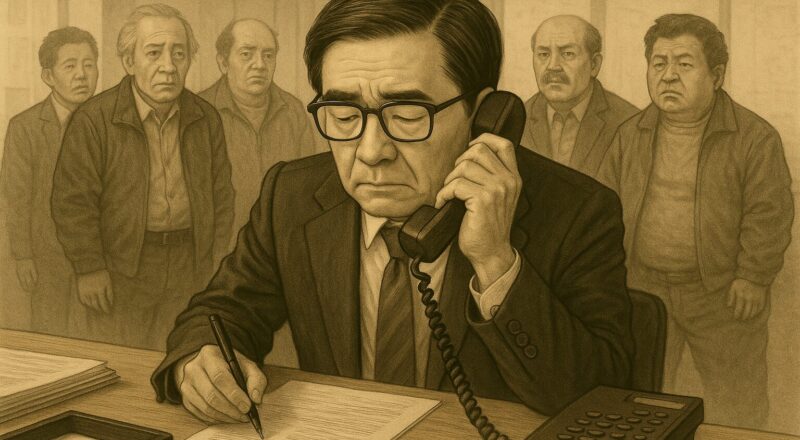何もなかった。
だが、すべてがそこにあった。
彼の名は、田山井光一(たやまいこういち)。
黒縁メガネに、地味なスーツ。
誰が見ても、街を歩けば5秒で忘れる顔。
声も小さく、滑舌も特段良いというわけでもない。
話し方は淡々としていて、他の「一発当てたる系」営業マンのエネルギッシュさとは一線を画していた。
初めてカンゾウ営業部に現れたとき、誰も期待などしなかった。
「地味なオッサン来たな」
それが、すべてだった。
◆
しかし──
タヤマイは、”続いた”。
日々同じ時刻に出勤し、毎日同じ調子で受話器を握り、雨の日も風の日も同じペースで電話をかけ続けた。
テンションを上げることもなければ、媚びることもない。
口八丁の嘘もつかない。
トークスクリプトに忠実に、淡々と電話の向こうの相手に話しつづけた。
ただ粛々と、電話をかけ続けた。

◆
カンゾウの営業部には、数多くの“派手な奴ら”がいた。
声のデカい者。
勢いだけで押し切る者。
豪快に笑い飛ばして、無理やり成約を取る者。
彼らは、ときに大きな契約を取った。
一夜にして、月収百万円を叩き出す者もいた。
だが──
彼らの多くは、続かなかった。
成約ゼロの月が3ヶ月も続くと、すぐに姿を消した。
瞬間風速は派手でも、それを「維持」する力は、なかった。
一方、タヤマイは、派手な月もない代わりに、ゼロの月も、ほぼなかった。
月に一人。
多いときで二人。
淡々と、契約を積み上げた。
それを、10年、いや20年近く続けていた。
◆
誰かが田山井に聞いた。
「どうして、そんなに続けられるんですか?」
タヤマイは、メガネの奥の目を細め、少し考えた後で、静かに言った。
「……たぶん、熱意、かな?」
それは、口だけの言葉ではなかった。
大声をだすわけでもなく、猫撫で声で媚びるわけでもなく、大風呂敷も広げない。
ただ、受話器を置かず、ただ、続けること。
その背中に、”本当の熱意”は、宿っていた。
◆
カンゾウの営業室では、今日も若者たちが鼻息を荒くし、一攫千金を夢見て受話器を握っている。
豪快な声が飛び交い、勢いで売ろうとする者たちの群れの中で、タヤマイは、静かに、いつも通り、電話をかけ続けていた。
誰よりも目立たず。
誰よりも折れず。
誰よりも、長く。
◆
──一瞬の栄光じゃない。
──続く強さ。
それを、誰よりも体現していた男の名前を、営業部の誰もが、静かに、敬意を込めて呼んだ。
──タヤマイさん、と。
第9話へ続く