第5話からのつづき
「ユウトさん、“目上の人に好かれる人間”って、どう思います?」
フクロウのアバターが、静かにもう一度首を傾けた。
「……え?」
ユウトの顔が、ほんのり驚きに染まる。
でも、ただの驚きではない。
小学生なりに、“何かの核心”に触れられたとき特有の、静かな緊張がにじむ。
Wは続ける。
「お父さんの会社の部長や課長──その肩書きやお給料は、お父さんが“自分で”決めたと思いますか?」
「……ううん、たぶん違う」
「学校の先生も、校長先生になるかどうかは、自分じゃ決められませんよね?」
「うん」
「政治家だって、テレビに出てる有名な人だって、“なりたい”だけでは、なれません」
「……うん」
「つまり、“誰かに選ばれる”という仕組みのなかで、私たちは生きている。
そして、選ぶのはたいてい“目上の人”です」
Wは、静かに、淡々と語っていく。
アバターの瞬きと、ゆっくりした首の動きが、不思議と語りのリズムを作っていた。
「もちろん、“使える人間”になる努力は素晴らしい。でも──“使えるだけの人間”は、“使い捨て”にもされやすい」
ユウトは思わず息を止め、胸の奥に冷たいものが落ちたように感じた。
「優秀な人は山ほどいます。東京大学に受かる人だけでも、毎年2000人以上います。卒業した人の数は、創立以来約30万人だそうです。でも、30万人すべてが特別なわけじゃなく、大半はやがて“普通の人”になります。」
「……優秀なだけじゃ、ダメなの?」
ユウトの声には、少し戸惑いがにじんでいた。
「そうです。“人間関係を作って維持する力”の方が、大人の世界では価値を持つことが多いのです」
ユウトの眉が、ほんの少し動いた。
「多少勉強ができなくても、挨拶がきちんとできて、素直で、明るい人のほうが、“次もお願いしたい”と思われることが多い。“優秀なだけの人”より、“感じのいい人”が選ばれることがあるのです。とくに、“決める側”の立場になると」
ユウトは、夢中で言葉を追うように身を乗り出した。
「優秀なだけの人は、山ほどいます。でも、結果的に“好かれる人”が生き残ることの方が多いんです」
Wは一拍おいて、少し声を柔らかくした。
「だからといって、“ゴマをすれ”とは言いません。でも、“目上の人に安心感を与える子”であることは、将来、いろんな場面であなたを助けるでしょう」
ユウトは、画面の向こうで、静かに何度か頷いていた。
「……でも、作文には何て書けばいいか、まだよく分かんなくて」
「そうですね。たとえば──“図書館の先生”がいいと思ったなら、それを書けばいい。でも先生が“もっと具体的に”と求めてきたときのために、“先生が安心する職業”を“準備”しておくのも、ひとつの作戦です」
「準備……?」
「たとえば、“医師”や“警察官”など、先生が“お、それは立派だね”と言いたくなるようなもの。それは“ウソ”ではなく、“先生との関係を良くする選択”です。作文は“将来の人生計画申告書”ではないんです。むしろ、“安心を渡すための言葉の選択”なんです」
ユウトは小さく息をのんだ。
「“将来の夢”は、将来見つかれば、それでいい。『何になりたいか』より、『どうありたいか』──難しい問いですが、大事なことですからね」
その言葉は、ユウトの胸にじんわりと落ちていった。
「それは、あなたの将来を先生が決めてしまうという意味ではなくて、“敵を作らずに、今を通り抜ける”という、知的な選択です」
言葉は淡々としていたが、不思議と温かさがにじんでいた。
「先生を“敵にしない”、それも立派な戦略ですからね」
ユウトは、少し考え込んだ様子で──そして、ふっと微笑んだ。
「……ちょっと、書けそうな気がしてきました」
「それは、よかった」
Wのアバターがゆっくりと一礼するように、首を傾けた。
次の瞬間──画面がストン、と消えた。
Zoomの接続が終了した。
──部屋に戻る。
和波知良(わなみかずよし)の書斎。
薄明かりの中、木製のローテーブルの上に、紙の箱が置かれている。
そっと開けると、つややかな栗がのった渋皮モンブラン。
傍らには、ネルドリップで淹れた深煎りのコーヒー。
ゆっくりと一口、苦味の奥に、ほのかな甘さがひろがる。
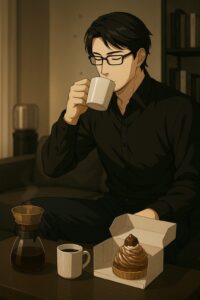
コーヒーの湯気が細く立ちのぼっては消えていった。
栗の香りに包まれながら、ふと一人の生徒の顔が脳裏をよぎる。
あの春の光景は、甘さでは覆い隠せないまま残っていた。
つづく
