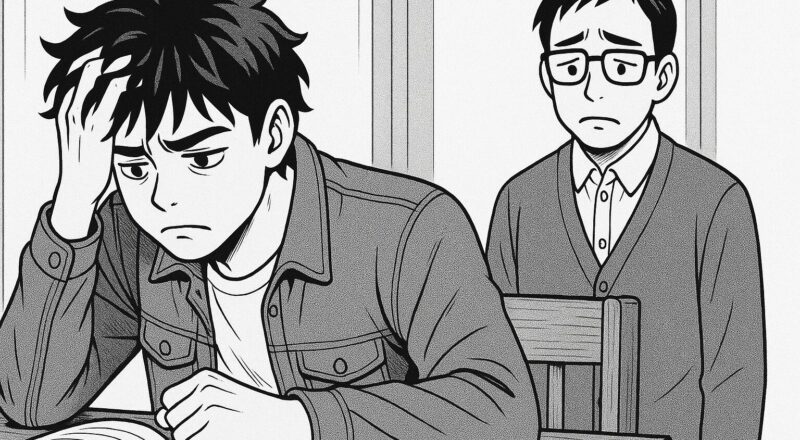──秋の気配が、じわじわとカンゾウを包みはじめた。
夏期講習が終わり、河口湖合宿からも戻ったリョウスケは、その頃から、少しずつ様子が変わり始めていた。
疲労が顔ににじみ、どこか集中力が切れているようだった。
秋の模試でも、成績は思うように伸びず、それがまた自信を削っていった。
「白井君、ちょっと時間とれるかな?」
カデノコウジが声をかけても──
「……今は、いいっす」
返ってくるのは、そっけない声だった。
リョウスケは目を合わせなかった。
カデノコウジは、リョウスケの姿を遠くから見るたびに、胸が苦しくなった。
声をかけたい。
もう一度、あの夏前のように、膝を突き合わせて勉強の話がしたい。
──でも、どうしても言葉が出てこなかった。
「今さら何を言っても遅いんじゃないか」
「無理に関わったら、かえって彼を追い詰めるだけじゃないか」
そう、自分に言い聞かせていた。
でも、本当はわかっていた。
ただ、自分が怖かったのだ。
夏に何もできなかった無力さ。
島田塾長の暴走を止められなかった責任。
あの瞬間から、もう、何かが壊れていた。
鏡を見ると、白髪がまた一筋、増えていた。
──冬。
最も大切な、最後の追い込みの時期。
だが、リョウスケが自習室に来る頻度が目に見えて減っていった。
日が短くなっていくのと比例するように、彼の姿は、どんどんカンゾウの中から消えていった。
カデノコウジは、指導室の窓から自習室を眺めるたびに、空いた席に目が留まり、唇を噛んだ。
(……すまない、白井君)
胸の中で、何度も謝った。
口に出せないまま、ただ、心の中で。
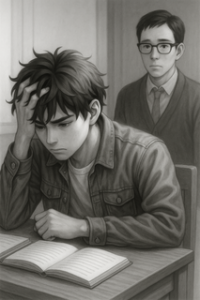
そして──入試本番。
リョウスケは、重い体と心を引きずるように、試験会場へ向かった。
鉛筆の走る音。
隣の受験生の咳。
冷たい空気。
すべてが、遠く、ぼんやりしていた。
集中しきれなかった。
最後まで、自信が持てなかった。
そして──不合格。
掲示板の前に立ったとき、リョウスケは、何も感じなかった。
「ああ、やっぱりな……」
そう思っただけだった。
家に戻る電車の中、ぼんやりと流れていく景色を見ながら、彼はただ、空っぽの気持ちで揺られていた。
カデノコウジは、その結果を聞いたとき、しばらく動けなかった。
言い訳はいくらでもできた。
原因だって、わかっていた。
だけど──
(俺の、責任だ)
カデノコウジは、そっと目を閉じ、またひとつ、白髪が増えた自分の頭に手をやった。
──声をかけたかった。
本当に、声をかけたかった。
でも、それができなかった。
すれ違ったままの冬は、
いつのまにか、静かに終わろうとしていた。
第13話へつづく