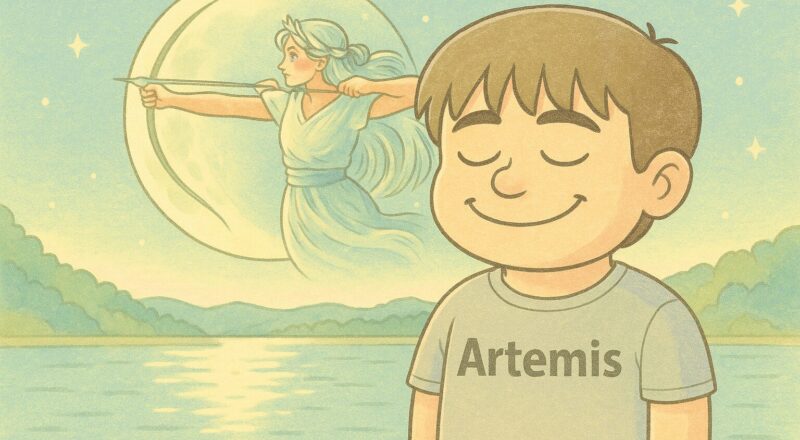避暑地・山中湖。
その湖畔に立つ、ログハウス風の豪華な別荘──それが、STXプレジデント・サギヤの所有する“フェニックス・リトリート”である。
空気は澄み、夜には湖に月が落ちる。
軽井沢ではありがちだが、ここでは月が、湖面にだけでなく、生徒の心にも映るらしい。知らんけど。
そんな話を合宿初日のオリエンテーションで語るのが、他でもない、引率講師ニッポリ研二である。
「え〜、みなさん。ここ山中湖にはですね、かつて縄文時代の“月見祭”があったとも言われています!この地で見る月は、ただの自然現象じゃない──魂の共鳴です!」
少しだけ風が吹いた。
生徒たちの多くはスルーか半笑いだったが、ニッポリは満足げにうなずく。
(よし……波動、届いてる)
この「STX月下合宿」は、毎年ごく限られた成績優秀者のみが招待される。
構成は、英語・数学・国語のガチ集中講義。
夜は座談会と講師との自由面談。
そして、時折、神のように降臨する、プレジデント・サギヤによる、超絶カリスマ化学講義 “デラックス理論”。
その授業が突然入るだけで、生徒たちは背筋を正すという。
そんな中、ニッポリの目に留まる一人の男子生徒がいた。
背は高め。細身で、髪は伸び気味。
周囲との会話は最小限。
ノートをとるときは妙に丁寧だが、笑顔はほぼない。
(……あれ?)
どこかで見覚えがある。いや、確か一昨年もいた気がする。
STXに出たり、高田馬場の予備校にいたという噂も聞いたことがある。
まるで、予備校の渡り鳥。
だが本人はそのことを一切語らない。
(……でも、なんか……雰囲気、今の僕に似てる)
そう思った瞬間──
記憶が動き出した。
ニッポリの記憶は20代半ばへと遡る。
そう、GMU留学時代の時へと。
場所は、アメリカ西海岸。夏の学期末、大学ではさまざまなアウトドアイベントが企画されていた。
カヌー&ピクニック
サマーBBQ
星空の下のキャンプファイヤー
Color Run
水鉄砲バトル
ミニ・スポーツフェス
みんなが笑っていた。走っていた。叫んでいた。
──そして、ニッポリは、その輪の外にいた。
「ハーイ、トニィ〜!」
「オーマイガー、サンドラ、ウェットすぎィ〜!」
そんな英語が飛び交う中、ニッポリはただ笑っていた。
笑っていたけど、言葉は出てこなかった。
伝わらなかった。
言葉も、気持ちも、タイミングも。
その結果、「……たぶんバングラディッシュの留学生」という目で見られるようになった。
えっと、日本人です。
心の中で何度も叫んだが、言えなかった。
英語がわからなかったわけじゃない。
でも、「話しかける勇気」が言葉に翻訳されなかった。
ハイキングの集合写真は、いつも端っこ。
BBQでも皿を洗う係。
カヤックでは、一人で漕いで帰ってきた。
心の中で何度も叫んでいた。
「俺だって……寂しいんだよぉ……!」
だが、その叫びは、誰にも届かなかった。
俺だって、俺だって、俺だって……
意識は、現在に戻る。
夜の山中湖。
月が照らすテラスで、彼が一人静かに星を見ていた。
ニッポリは、ゆっくりと彼に歩み寄った。
(あのときの俺のように、彼も叫べずにいるんじゃないか)
ニッポリは、しばらく彼の横に立ったまま、湖面の光を眺めていた。
言葉はなかった。
だが、どこかで自分を見ているような気がした。
あのとき、自分も、誰かに声をかけてほしかった。
そう思った瞬間、ゆっくりと、口が開いた。
「やあ……いい月だよね。なんていうか……今日はアルテミスの気配が濃い気がする」
「……はあ」
予想どおり、反応は薄い。
だが、ニッポリは負けない。
「月ってね、世界中でいろんな神話に登場するんだ。たとえば──ギリシャ神話だとアルテミス。狩りと月の女神さ」
「……そうですか」
(く、食いつかない……)
ニッポリは続ける。
「魂の波動ってね、実は月と連動してるんだ。今夜みたいな満月の夜は、“内なる音”が外に出やすくなる」
「……内なる音」
「そう!つまり、ソウルだよ。君にもきっと、ある。君だけのソウル」
沈黙。
「……いや、いいっす」
乾いた返事が、夜風に舞う。
ニッポリはそれでも笑顔を崩さない。いや、崩せない。
(……まあ、そういうタイプも、いるよね)
自分を納得させるようにそう呟くと、月を見上げた。
(俺って、やっぱり月向きの男じゃないのかな……)
──そして、数年後。
STX・鳳凰の間。
「おい、ヒッポリト星人!!」
「ニッポリです……」
いつものやり取り。
だが、サギヤの目は異様にキラキラしていた。
いや、ちょっと涙ぐんでさえいる。
「オレが育てた生徒が、ついにフェニックスの如く、世界に羽ばたいたぞ!!」
バンッとノートPCをテーブルに置く。
YouTubeの映像が再生される。
ステージ。うねるギター。魂のシャウト。沸き立つ観客。
画面にはこうあった。
“Live at Reading Festival”
Ryōsuke Shirai – The Soul from the Moonlit East
ニッポリの口が、ゆっくりと開く。
「え……あのときの、寡黙な彼が……?」
さらに画面を凝視する。
「確か、シライくん……リョウスケ・シライ……?」
映像は続く。
彼はステージで叫んでいた。
ギターをかき鳴らしながら、英語で、いや、魂で。
「This is my soul!! This is my sound!!」
観客が拳を突き上げる。
サギヤが言う。
「レディング・アンド・リーズ・フェスティバルっていやぁ、イギリスの歴史あるロックフェスティバルだそうだ!世界の中心で叫んだぞ、フェニックスが!!」
ニッポリは言葉が出なかった。
画面の向こうで、リョウスケ・シライは、確かに、自分の“内なる音”を響かせていた。
あの月の夜、伝わらなかったと思っていた言葉。
あのスピリチュアルな妄言の数々。
まさか……まさか、少しでも……
「……アルテミス、微笑んでたのかもな」
思わずつぶやいたその言葉に、サギヤが被せてくる。
「知らんけどな!!!」
-完-
next episode⇒エゾエ慎太郎の採用面接