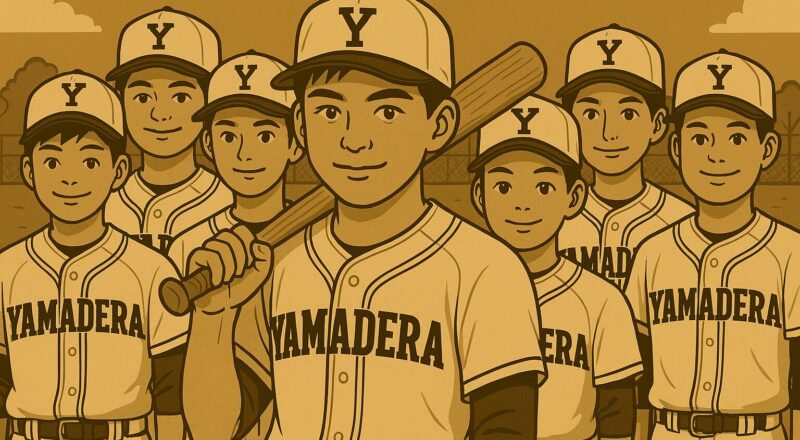──時代は1980年代。
甲子園のアルプス席では「サウスポー」と「狙いうち」が一日中鳴り響いていた頃。
高校野球は、“青春のすべて”だった。
地方都市にある私立高校──その野球部のキャプテンが、江添慎太郎(えぞえしんたろう)だった。

背番号「4」。
キャプテン。
4番バッター。
身長はそれほどない。
だが腕と腰のバネが違う。
県大会では、すでに3本のホームランを放っていた。
鋭い打球を打つ。肩も強い。
守備も堅実。
打って、抑えて、チームを勝たせる。
「小さな大砲。エゾエが打てば、試合は動く」
「チームの要」
「4番でエース──孤高の二刀流」
そんな記事を地元の新聞が書いた。
まるで、その勝利は自分だけの手柄のようだった。
「自分が打てば勝てる」
「自分が抑えれば勝てる」
エゾエはそう信じて疑わなかった。
チームが崩れても、自分が立て直せばいい。
誰かがミスしても、自分が打って黙らせればいい。
……だから。
「チームプレーなんて、結局“お飾り”だ」
そう思っていた。どこかで。
そして迎えた、夏の甲子園・初戦。
──高校三年・夏。
もう、後がない。
これが最後の甲子園だった。
県大会を勝ち抜き、ついに掴んだ夢の舞台。
対戦相手は、初出場の地方公立高校。
名前すら聞いたことがない。
野球部員はギリギリ9人、予選突破は“奇跡”とまで言われた高校だった。
「名前も聞いたことねぇな」
「楽勝っしょ」
「3回までに決めようぜ」
「今日ホームラン打てば、明日スポニチに名前出るぞ」
試合前、チーム内には、そんな空気が漂っていた。
エゾエは、そんな空気を嗅ぎながらも、バットを肩にかけて笑っていた。
(今日は俺の見せ場だ)
試合開始──初回、先制される。
盗塁、バント、スクイズ。小技の連続で、あっという間に0対2。
3回裏、エゾエの打席。
──内角直球。見逃し三振。
ベンチに戻った瞬間、どこかで小さく溜息が聞こえた。
5回の守備では、チームメイトの送球ミスから2点追加される。
6回、1点を返すも、続く8回に──満塁弾を打たれ、1対9。
試合終了。コールド負け。
甲子園の空は高く、バックスクリーンの向こうには、知らない旗が揺れていた。
あの“無名校”の旗だった。
整列の時、エゾエはまだ理解できなかった。
「なんで……俺がいるのに、負けたんだ?」
相手校のユニフォームは土だらけだった。
監督は、まるで農協のオジサンのような風貌だった。
だが、握手をしたときの手のひらは分厚く、柔らかく、温度があった。
「おつかれさん、キャプテン。いい選手やな」
そう言われた瞬間、
(ああ、これは“俺の負け”じゃない──“チームの敗北”なんだ)
と、ようやく胸に落ちた。
(……俺ひとりががんばっても、勝てねぇ試合がある)
(俺が“いれば”勝てるんじゃない。“皆が役割を果たす”ことで、勝てるチームになるんだ)
──夏は、終わった。
帰りの新幹線。
通路を挟んで座る控え選手が泣いていた。
エゾエは窓の外を見ながら、ひとり、唇を噛んだ。
窓に映った自分の顔は、今までで一番悔しそうだった。
(……俺は“4番”じゃなかった。俺は“キャプテン”だったはずだ)
(それなのに──)
数日後、引退が決まり、部室のロッカーに戻ると、顧問からの一冊の本が紙袋に入っていた。
『勝たせる監督術──地方公立校からの挑戦』
──著者:あの時、握手を交わした相手校の監督。
家に帰ってページをめくる。
「バントの練習に、3ヶ月かけた」
「9人全員が、送りバントを確実に決められるようになったとき、初めて“このチームは戦える”と思った」
「スターはいらない。一塁を踏み、球を止め、指示を聞く。そんな“名もなき選手”が9人そろえば、野球は勝てる」
「役割のない選手はいない。ないとすれば、それは監督が見抜けていないだけだ」
野球ノートは、もう閉じた。
けれど、監督ノートが、その日から始まった。
バットは握っていなかったが、彼の心の中では、次の試合が始まっていた。
第6話へつづく