高校野球を引退したあと、エゾエはスポーツ推薦で都内の中堅私立大学に進学した。
経営学部に所属し、野球部にも入った。
だが、そこにはもう、かつてのような“燃える何か”はなかった。
「野球じゃない”何か”を学ばなければ」
あの夏を境に、彼の思考は変わっていた。
彼は、組織論にのめり込んだ。
「勝てるチームとは何か」
「勝たせる監督はどう動くのか」
あの敗北から、彼は指揮官の役割に目を向け始めていた。
卒論のテーマは、『監督論から読み解く組織マネジメント』。
野球部員たちは、「え?お前、野球やってんのに監督の方いくの?」と笑った。
エゾエは苦笑いで返しながら、講義後の図書館に籠った。
孫子の兵法、組織心理学、クラウゼヴィッツの『戦争論』。
あらゆる「組織と戦略」に関する本を片っ端から読んだ。
就職先に選んだのは、信用金庫だった。
「なぜメガバンクじゃなく、信用金庫なんですか?」
面接でそう問われ、彼はこう答えた。
「チーム戦で活躍したいと思いまして。」
「どういうことですか?」
面接官が身を乗り出す。
「メガバンクは、個人の専門性や能力がモノを言うかもしれません。でも、地元密着型の信金では、職員が一丸となって地域をサポートするチームワークと、信用の積み重ねが重要視される世界だと感じました。つまり私は、地道に信用を積み上げていく組織で働きたいと思ったんです」
採用担当者は、ポカンとしていたが、数週間後、彼には内定通知が届いた。
信用金庫での業務は地味だった。
法人営業、融資書類の作成、預金の集計…。
上司は言った。
「エゾエくんは無駄がないね。後輩の面倒もよく見てる。将来、支店長は確実だよ」
でも、エゾエの心のどこかは、乾いていた。
(もっと“仕組み”を作れる場所に行きたい)
(プレイヤーじゃなく、“監督”になりたい)
そんなとき、融資を担当していた取引先の学習塾の社長から声をかけられた。
「うちの塾、経理と総務がグズグズでね。マネジメントもできる人材を探しててさ。どう?」
エゾエの心は動いた。
「教育業界ってのは、人材がすべてだからね」と、塾の社長は笑顔でそう言った。
迷いはなかった。
彼はその学習塾に転職した。
ここから、エゾエの教育業界での修行が始まる。
小さな塾だった。
地元密着型。教室数は2つ。社員は8人。
高校受験を中心に、地元の中学生を集めて授業をする。
予備校と学習塾の中間のような場所。
エゾエはここの総務部で、庶務と人事を任されることになった。
入社1年目。
教材も作った。タイムカードも導入した。教室のレイアウトも見直した。
しかし、現場は甘くなかった。
エゾエが驚いたのは「講師」という人種だった。
夜、22時。
授業は21時で終わっているはずなのに、講師の一人がまだ教室を占拠していた。
「すみません、もう閉館時間なんで……」
若いスタッフが声をかけると、講師は怒鳴った。
「こっちは生徒のために授業してんだよ!残業代?いらねぇよ!」
その後、帰れなかったスタッフたちに残業代が発生し、余計な人件費がかかることになった。
「うちの子、まだ帰ってこないんですけど、いつまで拘束するつもりですか?」
このような保護者からのクレームに対応するのも塾のスタッフたちだった。
こういうことは日常茶飯事だった。
結果、塾の無駄な人件費と社員のストレスが膨らんでいく。
ある日、30代の数学の講師が自慢げにこう語っていた。
「いや〜、今日の子、数学の偏差値48だったのが、俺の授業で58ですよ。10アップ!」
「俺が入れたも同然っすよ、マジ感謝されましたから!」
別の若手講師もこう言う。
「オレの授業で受かったって、あいつら言ってたよ」
「この生徒、完全に俺が育てたからね。成績、ぜんっぜん違うから」
スタッフルームで講師たちが語る“俺の手柄自慢”に、エゾエは背筋が冷えた。
(誰のための教室だ?)
授業は延長する。
ルールは守らない。
感情優先。
「これは教育じゃなくて、承認欲求の代行業みたいだな……」
その夜もまた、授業が終わるまで教室を閉められず、結局、社員が授業が終了し、講師が帰るまで待機することになった。
社員がつぶやいた。
「授業が終わらないと、帰れないのよね……。あの人たち、自分が主人公だと思ってるから」
別の社員もこう返す。
「皆さん、自分の科目で生徒を受からせたと言いますよね…」
エゾエはため息をつく。
(一つの科目で入試に合格できるわけないだろ…。)
一つの科目、、、
一つの、、、
そこでエゾエは愕然とした。
(……まるで、あの頃の俺だ)
自分一人が活躍すれば、チームは勝てると思ってた頃の──。
講師たちは言った。
「生徒に泣いて感謝されると、こっちも泣きそうになりますよね」
「俺、教えながら“ああ、今、生徒の未来が変わってるな”って感じるんですよ」
それはまるで、舞台の上の俳優のようだった。
だが、現実はどうか。
授業のレベルは高いかもしれないが、報告連絡はなし。
担当科目を越えて、生徒に余計なことを教える。
他の講師との連携はゼロ。
それでいて、「生徒に好かれてるのは自分だけだ」と信じ込んでいる。
彼らのせいで、チームが乱れる。
講師一人の“熱意”が、塾全体の“混乱”を生んでいた。
「こういう奴らを、戦力にはできない」
エゾエは思った。
「規律とルールの中で、最高のパフォーマンスを出せる人間が──本物だ」
彼は少しずつ、自分の組織哲学を言語化していった。
・自己陶酔型を入れてはいけない
・“熱意”と“規律”のバランスを見極めろ
・スタンドプレイはチームを壊す
・独善講師は、熱心そうに見えて“最大のリスク”だ
こうして、彼の“組織観”は磨かれていった。
人事評価表。
講師会議。
担当科目とカリキュラムのすり合わせ。
講師同士の相性。
生徒のタイプ別分類。
情報の横流しの抑止。
「見える化」「共有」「連携」
──この三本柱を軸に、“教育オペレーション”を再構築していく。
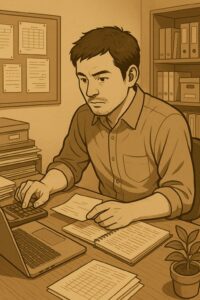
そして、5年後。
彼のチーム運営は業界内でも評価されるようになる。
ある日、ひとりの男がエゾエの前に現れた。
濃い眉毛。細い目。
開口一番、男はこう言った。
「エゾエさん。うちに来てください。うちはね、“猛獣”を飼ってるんです。でもね、猛獣って、ちゃんと檻に入れて、エサを与えて、しつければ、一番の戦力になるんですよ」
男の名は、カトウ。
医学部専門予備校「メディカルデラックス」の代表だった。
「大学受験は“個人戦”じゃない。集団戦です。でも今の受験業界は、スタープレイヤー至上主義。講師の“顔”で生徒を釣る。だが、それには限界がある」
エゾエは頷く。
「うちにも、いますよ。“オレが早稲田に入れた!”とか“俺の授業で全員合格!”とか言い出す講師が。でも、やらせっぱなしじゃダメなんです」
カトウも頷く。
「現場には、監督が必要なんです。エゾエさん、あなたにやってほしいんです。“教育現場の後方指揮官”を」
その夜。
エゾエはひとり、塾の屋上に立った。
遠くに見える夜景。
風が強い。
目を閉じると、あの日の甲子園が蘇る。
グラウンドを駆け抜けた仲間の背中。
自分に声をかけた「あの監督」の手のひら。
組織の現場には「監督」が必要だ。
それは、野球でも、教育でも同じだ。
(俺の道は……ここだったのかもしれない)
そう思った瞬間、口元に笑みが浮かんだ。
教育現場の後方指揮官・江添慎太郎。誕生の瞬間だった。
第7話へつづく。
