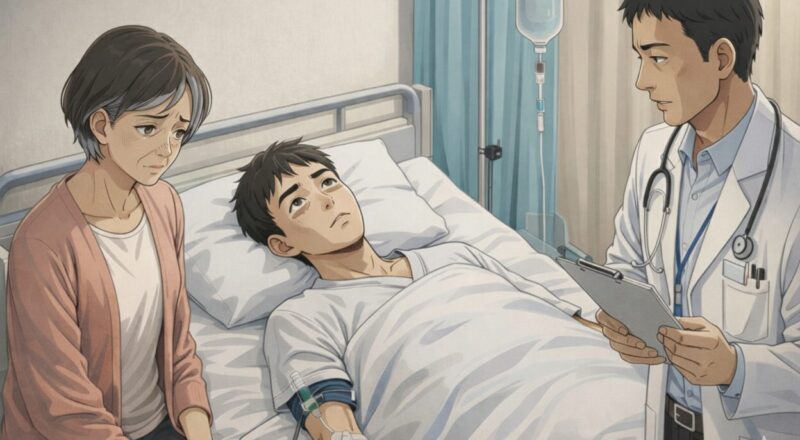その朝、ダイキはプレゼン資料の修正を終え、ようやく席を立った。
時刻は午前3時過ぎ。椅子の背もたれに体を預けた瞬間、視界がぐにゃりと歪んだ。
「……あれ?」
立ち上がろうとしたその瞬間、膝が抜けるように力が入らなくなり、床へ、静かに崩れ落ちた。
遠ざかる天井の灯り。
誰かの足音と、自分の名前を呼ぶ声が、遠くに聞こえた気がした。
病院のベッドで目を覚ましたとき、ダイキは白い天井を見上げていた。
点滴の針が右腕に刺さっている。
その横で、母親が泣きそうな顔で彼を見つめていた。
「ダイキ……あんた、なんでここまで……」
言葉が出なかった。
喉はカラカラに乾き、頭は鈍く痛む。
体を動かす気力もなく、ただ、天井をぼんやりと見つめることしかできなかった。
数日後、医師からこう言われた。
「診断結果ですが、過労による脱水と栄養失調、それに加えて適応障害の疑いがあります」
仕事のストレスが、限界を超えていた。
不眠、倦怠感、食欲不振、強い不安感――
それはすべて、心が発するSOSだった。
「まずは3ヶ月間、しっかり休んでください。仕事のことは忘れて、とにかく身体と心を回復させましょう」
そう告げられても、ダイキはすぐには納得できなかった。
仕事を休むなんて。
プロジェクトはどうなる。
あの会議、あのレポート、あの進捗管理。
だが、体が先に限界を認めていた。
彼は観念して、休職を決意した。
休職の最初の1週間は、ほとんど寝ていた。
朝も昼も関係なく、何も食べず、ただ眠り続けた。
夢も見ないほど、深く。
2週目に入ると、ふと近所の公園に足を運ぶようになった。
ベンチに座り、ぼんやりと空を眺める。
カラスの鳴き声すら、新鮮だった。
やがて実家に戻り、母親の作った味噌汁をゆっくり噛みしめる時間が戻ってきた。
何も考えずに本を読んだ。
大学時代に好きだった司馬遼太郎や、池波正太郎の文庫本。
1ページ読むごとに、心の奥の硬さがゆっくりと溶けていくようだった。
休職から2ヶ月が過ぎた頃。
ダイキは1枚の白紙に線を引いた。左右にスペースを分け、タイトルを記した。
「ベイカーで得たもの」
「ベイカーで失ったもの」
得たものは、論理的思考、膨大な知識、一流との仕事、高収入、ブランド。
失ったものは、健康、睡眠、プライベート、自己肯定感、人生の幅。
見比べて、静かに息を吐いた。
(俺は……どこに行きたかったんだろう)
転職サイトで、ふと「教育」と検索してみた。
ヒットしたのは、いくつかの学習塾や予備校の求人情報。
大手ではない中小の塾が多く、年収は今の半分以下だった。
だが、「生徒の成長を支援する」「未来の担い手を育てる」という言葉に、なぜか胸がじんとした。
その夜、ダイキはベッドに寝転びながら、自分に問いかけた。
(教えるって……ロジックの伝達とは違うのか?)
(コンサルと違って、“人”と向き合うことが中心なんだろうか)
次第に、「講師」ではなく、「担任」や「コーチ」といった言葉が心に引っかかってきた。
それは、プロジェクトの成功を目指してチームを率いた日々と、どこかで似ていた。誰かの課題に向き合い、気持ちに寄り添い、次の一手を一緒に考える。それは、“教育版のコンサルティング”とも言える。
3ヶ月の休職期間が明ける前、ダイキは退職届を提出した。
もう、あの場所には戻らない。
華やかで刺激的だったが、あまりに高く、遠く、自分を削りすぎる場所だった。
これから向かうのは、まったく別の世界。
だが、決して後ろ向きではなかった。
自分の持っているスキルを、“人の未来”のために使う仕事。
それが、いまのダイキの再起の場所になると信じていた。
第4話へつづく